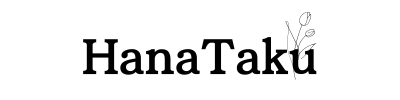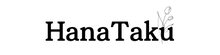お盆は年に一度ご先祖様の霊を迎えて供養する日本人にとって大切な期間です。その際に欠かせないのが「お供え花」。中でも、ミソハギ(禊萩)は古くから「精霊花(しょうりょうばな)」として親しまれ、お盆特有の意味合いを持った特別な花とされています。
この記事では、ミソハギとはどんな花なのか、なぜお盆に飾るのかといった基本情報から、仏壇やお墓での飾り方、他の供花とのアレンジ方法、購入のタイミングやマナーまでを解説します。ミソハギを通して、心を込めたお盆の準備を進めましょう。
ミソハギとはどんな花?特徴と基本情報

| 科名/属名 | ミソハギ科ミソハギ属 |
| 和名 | 禊萩 |
ミソハギ(禊萩)は、ミソハギ科に属する多年草で、7月から9月にかけて紫紅色の小さな花を穂のように咲かせる夏の花です。特にお盆の時期と開花期が重なることから、古くから仏前に供える「精霊花」として親しまれてきました。
この花の特徴はすっと伸びた細長い茎に小さな花が整然と並ぶ清楚な佇まいと、水辺でもよく育つ強さです。田んぼの畔や湿地帯に自生することが多く、水との関わりが深い植物です。そのことから「清めの花」としての意味合いが強く、お盆の儀式や供養の場にふさわしいとされています。
また、草丈は30〜80cmと比較的扱いやすいサイズで、花瓶に活けたり、墓前に供えたりするのにも適しています。
【関連記事】お盆のお供えする花の種類は?12種類のおすすめをご紹介
なぜお盆にミソハギを飾るのか?その意味と由来
お盆の花としてミソハギが重宝される背景には、宗教的・文化的な意味が色濃く反映されています。
「ミソハギ」という名前の由来の一説は、「禊(みそぎ)」という言葉にあります。古来、日本では水によって穢れを祓い、清らかな状態で先祖の霊を迎えるという風習が根づいていました。ミソハギは、そんな“水による浄め”を象徴する花とされてきたのです。
具体的には、以下のような意味合いがあります:
-
迎え火・送り火の際、霊を清めるために使う
-
仏前や墓前を水で清める儀式に用いられる
-
「精霊花」として、霊を慰める花としての役割を担う
実際に、ミソハギの枝を束ねて水に浸し、それで仏前の供物や墓石に水を垂らしながらお参りするという風習は、今も一部地域に残っています。
ミソハギは「静かに心を整え、霊と向き合う花」として、他の供花とは少し異なる精神的な役割を果たしてきました。
【供花】ピンク色のトルコキキョウ入り紫色・ピンク色のお供え花束 5,000円 ピンクのトルコキキョウが入った上品で優しい印象の定番サイズのお供え花束 ¥5,500
【商品一覧】お盆に贈るお供え花
ミソハギの飾り方と使い方|仏壇・精霊棚・墓前それぞれの例

仏壇での飾り方
ミソハギは、仏壇に供える仏花としても広く用いられます。基本は、左右対称になるよう花瓶に活け、供物や仏具とのバランスを見て配置します。草丈があるため、仏壇の高さに合わせて茎をカットし、見栄えよく整えるのがポイントです。
白菊やカーネーションと組み合わせることで、色彩の調和が取れ、上品で落ち着いた雰囲気になります。
精霊棚(しょうりょうだな)での使い方
精霊棚は、お盆の期間にご先祖様の霊を迎えるために設けられる特設の祭壇です。ミソハギは、中央または供物の横に小さな器(竹筒やグラス)に挿して飾るのが一般的です。
精霊馬やほおずき、リンドウなどと一緒に並べることで、季節感と厳かさを兼ね備えた供え方になります。
墓前での使用
ミソハギは花持ちが良く、多少の風にも耐えるため、墓前用の供花としても適しています。花筒に単体で挿しても良いですし、他の仏花と合わせてボリュームを出すのも効果的です。
また、地域によっては、ミソハギの枝に水を含ませて墓石を清める風習もあるため、参拝の際の“清めの花”としても活躍します。
【商品一覧】新盆・初盆に贈るお供え花
ミソハギと他の供花と組み合わせるならどんなお花がおすすめ?

ミソハギは控えめでありながら凛とした存在感があり、他の供花との相性も良い花です。以下のような花との組み合わせがおすすめです:
-
白菊・小菊:清らかさを象徴する定番の供花。ミソハギの紫と美しく調和し、仏花としての格式を保てます。
-
ほおずき:提灯に似た姿が先祖の道しるべとされるほおずきは、ミソハギの落ち着いた色調に明るさを添えます。
-
リンドウ:同じ紫系の色合いで、花の形や濃淡の違いが美しいコントラストを生み出します。
-
スターチス:ドライにもなる花で日持ちが良く、アレンジのベースやボリュームアップに重宝されます。
花瓶やカゴにアレンジする際は、高低差や色の配置を工夫することで立体感と奥行きのある供花に仕上がります。清楚で格式を感じさせるお供えとして整えると、仏前にも丁寧な印象を与えられます。
【関連記事】お盆の花にほおずきを選ぶ理由とは?意味・飾り方・マナーまで解説
【供花】ピンク色のトルコキキョウ入りピンク色のお供え花束 5,000円 ピンクのトルコキキョウが入った優しい印象の定番サイズのお供え花束 ¥5,500
ミソハギを購入するタイミングと価格帯の目安
ミソハギは、夏の花として7月下旬から8月にかけて市場に出回ります。お盆前の時期には花屋やスーパー、生花直売所などで広く販売されるため、タイミングを逃さず準備しておくと安心です。
購入先の例
-
地元の花屋
-
スーパーの切り花コーナー
-
朝市・農産物直売所
-
オンラインショップ(仏花セット含む)
価格帯の目安
| 商品タイプ | 価格帯の目安 |
|---|---|
| 切り花1束(5〜10本) | 300円〜800円前後 |
| アレンジメント含む仏花セット | 1,500円〜3,000円程度 |
購入時は、茎がしっかりしていて、花がしおれていない新鮮なものを選びましょう。葉の先端が黄色くなっていないか、花が開ききっていないかなどもチェックポイントです。
ミソハギを飾る際のマナーと注意点

ミソハギを供花として使う場合、以下の点に注意しましょう:
-
本数は奇数で:仏事では3本・5本など奇数が縁起が良いとされます。
-
水をたっぷり与える:湿地植物なので乾燥に弱く、水を絶やさないようにします。
-
他の花とのバランスを意識:丈が高めなので、周囲の花との高さや色合いの調整が必要です。
-
香りが控えめ:香りの強い花ではないため、仏前や室内でも使いやすいです。
-
地域の作法に配慮:一部地域では「水引きの儀式」に使う場合があり、作法に沿って丁寧に扱いましょう。
【供花】白色・ピンク色のお供えアレンジメント 10,000円 柔らかな色合いで偲ぶ、命日や法要にふさわしい落ち着いた美しさのお供えアレンジメント ¥11,000
よくある質問Q&A
Q. ミソハギだけを飾っても問題ありませんか?
A. 問題ありません。単体でも凛とした雰囲気があり、お供えとして十分成立します。ですが、白菊やスターチスなどと組み合わせるとより華やかに整います。
Q. 小さい仏壇でも飾れますか?
A. ミソハギは丈があっても切り分けやすいため、小さな花瓶やグラスに数本だけ飾るという工夫でスペースに対応できます。
Q. 地域によってミソハギを使わないこともありますか?
A. はい、ミソハギの使用は地域差があります。西日本や東北の一部ではよく使われますが、都市部や関東ではあまり馴染みがない地域もあります。地域の風習や家族の意向を優先しましょう。
まとめ|ミソハギに込める祈りとお盆の心

ミソハギは、お盆の時期に欠かせない「精霊花」として、古くから日本人の心と供養の場に寄り添ってきた特別な存在です。水辺に咲く姿と清らかな印象から、霊を迎えるにあたっての“清め”の象徴とされ、他の供花にはない静かな力強さを備えています。
仏壇や精霊棚、お墓参りなど、供える場所やシーンに応じて飾り方を工夫し、心を込めて準備することで、故人やご先祖様への想いをより深く伝えることができるでしょう。
今年のお盆には、ぜひミソハギの清楚な佇まいを取り入れて、心穏やかなひとときをお過ごしください。