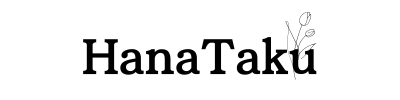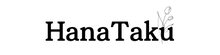故人を偲ぶ気持ちを形に表す「お供え花」。その選び方には宗教や地域、供える場面ごとのマナーが伴います。「どの花を選べば失礼がないのか」「宗派による違いはあるのか」など、不安や疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
本記事では、定番のお供え花の種類をはじめ、選び方、タブーとされる花、マナーや贈る際の注意点までを解説します。大切な方への感謝や祈りが花を通してきちんと伝わるよう、参考にしてください。
供花とは?基本的な意味と目的
 供花(きょうか/くげ)とは、故人への哀悼の気持ちや、これまでの感謝、敬意を込めて手向ける花のことを指します。通夜や葬儀、法要、命日、お盆、お彼岸など、故人を偲ぶさまざまな場面で供えられます。
供花(きょうか/くげ)とは、故人への哀悼の気持ちや、これまでの感謝、敬意を込めて手向ける花のことを指します。通夜や葬儀、法要、命日、お盆、お彼岸など、故人を偲ぶさまざまな場面で供えられます。
供花には、亡くなった方の安らかな旅立ちを願う想いと、残された人々の悲しみや祈りをそっと支える役割があります。目に見えるかたちで気持ちを届ける手段として、また、故人を忘れないという心を表すものとして、長く大切にされてきました。
花を供えるという行為には、言葉にしきれない思いを優しく伝える力があります。色や香り、佇まいが、張りつめた場にやわらかさを添え、ご遺族の心にもそっと寄り添います。
供花は、ただ美しいものを飾るのではなく、故人を思い、相手をいたわる気持ちを込めて贈る、心のこもった弔意のあらわれといえます。
【関連記事】お供え花に添える立て札の例・書き方|連名の場合はどうする?
お供えに適した花の種類一覧
供花として選ばれる花には、見た目の美しさだけでなく、意味や耐久性、季節感などの要素も重要です。以下は、よく使われる代表的な供花の種類をご紹介します。
菊(スプレーマム・輪菊)

花言葉:清らかさ・高貴・不老長寿
仏教において非常に格式の高い花とされる「菊」は、古くから供花の定番。白い輪菊やスプレーマム(小菊)は、故人の冥福を祈る場面にふさわしく、和洋どちらのアレンジにも馴染みます。
-
おすすめのシーン:初七日・四十九日・年忌法要・お墓参り・男性へのお供え
-
特徴:花もちが良く、真夏や冬でも比較的長持ちするため、屋外(墓地など)にも向いています。
ユリ

花言葉:純粋・無垢・威厳・再生
香り高く、華やかな姿のユリは、白を基調にしたお供え花によく使われます。特に白ユリは清楚で気品があり、仏式やキリスト教式の葬儀・告別式にもよく用いられます。
-
おすすめのシーン:通夜・葬儀・四十九日・命日・女性へのお供え
-
特徴:1本でも存在感があり、アレンジメントに上品さを加える花材です。
【供花】白色・ピンク色のお供えアレンジメント 10,000円 柔らかな色合いで偲ぶ、命日や法要にふさわしい落ち着いた美しさのお供えアレンジメント ¥11,000
カーネーション

花言葉:無垢で深い愛・感謝
カーネーションは「母の日」のイメージが強いですが、優しさや慈しみを表す供花としても最適です。故人が女性の場合や、感謝の気持ちを表したい場面に選ばれることが多いです。
-
おすすめのシーン:お盆・命日・母親や祖母のお供え・女性への贈り物
-
特徴:色の種類も豊富で、アレンジしやすく、花もちも良好。
トルコキキョウ

花言葉:優美・希望・感謝
柔らかな花びらと豊かな表情を持つトルコキキョウは、性別や宗教問わず使いやすい万能な花材です。特に夏場の暑さにも比較的強く、花もちが良い点でも人気です。
-
おすすめのシーン:通年の供花・お盆・命日・故人を偲ぶ家庭での飾り花
-
特徴:色も豊富で、他の花との相性も良いため、ナチュラルなアレンジが可能。
リンドウ

花言葉:誠実・悲しみに寄り添う・正義
秋に旬を迎えるリンドウは、落ち着いた紫色で、供花全体に引き締まった印象を与えます。故人への誠実な想いを表す花として、秋のお彼岸や男性の法要で好まれます。
-
おすすめのシーン:お彼岸(秋)・男性の法要・四十九日・お墓参り
-
特徴:深い色味がアレンジに重厚感を加えるアクセントに。
スターチス

花言葉:変わらぬ心・永遠の記憶
色あせにくく、ドライフラワーになっても美しいスターチスは、「想いを長く残したい」場面にぴったりです。メイン花材というよりは、アレンジの中のサブ素材として重宝されます。
-
おすすめのシーン:お盆・命日・永年供養・枕花や室内での長期供花
-
特徴:紫や白が多く使われ、ナチュラルな雰囲気が人気。
胡蝶蘭

花言葉:幸福が飛んでくる・尊敬・高貴
白い胡蝶蘭は、気品と清潔感を兼ね備えた高級感のある花。特に法人や団体からの供花として人気が高く、葬儀や告別式、通夜に贈られることが多いです。
-
おすすめのシーン:通夜・葬儀・法人からの供花・高齢者へのお供え
-
特徴:鉢植えで贈ることも多く、格式ある贈り物として好印象を与えます。
ケイトウ

花言葉:おしゃれ・個性・永遠の命
ユニークな形状とビビッドな色合いが特徴のケイトウは、最近では洋風アレンジに多く取り入れられるようになっています。見た目に個性があるため、明るい雰囲気のお供えにもおすすめです。
-
おすすめのシーン:個性的なアレンジを希望される方・洋風の室内供花
-
特徴:赤・ピンク・黄色など鮮やかな色が特徴。暑さにも比較的強いです。
デルフィニウム

花言葉:清明・希望・あなたは幸福をふりまく
デルフィニウムは青や紫の花が美しく、アレンジに涼しさや洗練された印象を与えます。男性向けの供花や初夏の法要などに使われることが多い花です。
-
おすすめのシーン:男性の命日・初夏の法要・青系カラーで統一したい場合
-
特徴:縦にボリュームが出るので、高さのあるアレンジにもおすすめです。
アルストロメリア

花言葉:持続する愛・献身・友情
柔らかな印象で日持ちも良いアルストロメリアは、供花にも多く使われています。ボリュームが良いため、大きさを重視する際にはおすすめです。
-
おすすめのシーン:自宅用のお供え・男性、女性向け
-
特徴:カラーバリエーションが豊富で、仏花に色味を加えるアクセントとして活躍。
アスター

花言葉:追憶・信じる心・思い出
アスターは小ぶりながらもかわいらしく、花束やアレンジの「脇役」としても存在感を発揮する花です。優しい印象を与えたいお供えに適しています。
-
おすすめのシーン:女性やお子さまへのお供え・家庭でのアレンジ
-
特徴:ピンク・白・紫など多彩な色で、優しさや親しみやすさを演出できます。
デンファレ
花言葉:おもてなし・魅力的な人・純粋な愛情
デンファレは、南国の雰囲気を感じさせる洋ランの一種で、涼やかな印象とともに、清らかさや優雅さを併せ持つ花です。茎が長く、軽やかな花付きなので、お供え用のアレンジメントに動きを出したいときによく使用されます。
-
おすすめのシーン:夏場の命日やお盆・女性への供花・涼しげな印象を与えたい場合
-
特徴:暑さに比較的強く、花もちがよいのも魅力。白や紫を基調としたものが多く、仏花にもなじみます。洋風・和風どちらのアレンジにも合わせやすく、見た目にも涼しさを添えてくれます。
-
ポイント:お供えの中に軽やかさや清涼感を加えたいときにぴったり。特に夏の時期の女性の命日やお盆飾りに人気があります。
カラー

花言葉:華麗なる美・清浄・乙女のしとやかさ
すらりとした立ち姿と、洗練された花姿が美しいカラーは、モダンでスタイリッシュな印象を与えるお供え花として人気があります。白をはじめ、ピンク・紫・黄などの品種もありますが、供花としてはやはり「白」が定番です。
-
おすすめのシーン:四十九日・キリスト教式の追悼・女性の命日・シンプルな仏花
-
特徴:清潔感があり、曲線的なラインが美しく、シンプルかつ上品な供花に仕上がります。フォーマルな雰囲気にも合うため、格式のある場でも使いやすい花材です。
-
ポイント:見た目の美しさだけでなく、花言葉も「清浄」「しとやかさ」といった供花にふさわしい意味を持つため、特に女性の法要や命日、静かに故人を偲ぶ場面におすすめです。
【供花】ピンク色のトルコキキョウ入り紫色・ピンク色のお供え花束 8,000円 ピンクのトルコキキョウが入った上品で優しい印象の華やかさと落ち着きを兼ねそろえたお供え花束 ¥8,800
【関連記事】お供え花のメッセージカードの例文・書き方・マナーをご紹介します
お供え花で避けるべき花・タブー
お供え花を選ぶ際には、「ふさわしい花」を選ぶことと同じくらい、「避けるべき花」を把握することも大切です。見た目が美しくても、意味や性質によっては弔事にそぐわないとされる花も存在します。
うっかりタブーを犯してしまうと、贈った相手やご遺族に不快感を与えてしまう可能性もあるため、以下のような花はできるだけ避けましょう。

トゲのある花(例:バラ・アザミ)
理由:トゲは「殺生」や「痛み」、争いの象徴とされるため
バラをはじめとしたトゲのある植物は、たとえ美しい花であっても弔事の場には不向きとされています。特に仏教においては、殺生や苦しみを連想させるものは供養の場にそぐわないと考えられています。
-
注意点:一部ではトゲを取って使用するケースもありますが、基本的には避けた方が無難です。
-
代替案:同じような華やかさを求めるなら、カーネーションやトルコキキョウなどトゲのない花がおすすめです。
毒を持つ花(例:スズラン・ヒガンバナ・チューリップの球根)
理由:見た目に反して有毒な成分を含むものは「死」や「不吉」を連想させるため
スズランは香りも良く可憐な花ですが、全草に毒性があるため仏壇や室内供花には不向きです。同様に、ヒガンバナ(彼岸花)も「死人花」「地獄花」などと呼ばれることから、縁起を担ぐ場面では避けられがちです。
-
注意点:小さなお子様やペットがいる家庭では、毒性のある花材は安全面でも懸念されます。
-
代替案:香りが穏やかで毒性のないスターチスやリンドウなどが安心です。
香りが強すぎる花(例:香りの強いユリ・ジャスミン・ラベンダー)
理由:お香や線香の香りと混ざり、不快に感じる場合があるため
供花に香りのある花を使用するのは決してNGではありませんが、香りが強すぎると場の空気を乱したり、ご遺族の体調を害する場合もあるため注意が必要です。とくに密室になる仏間では香りがこもりやすく、線香やお香の香りと混ざることで不快に感じられることもあります。
-
注意点:香りの強い品種を避け、さりげない香りの花を選ぶのがマナーです。
-
代替案:ユリを使う場合は、香りの少ない品種を選ぶとよいでしょう。
花粉が多く散る花(例:一部のユリ・アマリリス)
理由:仏壇や遺影の周りを汚す原因になるほか、アレルギーや不快感を招く可能性があるため
美しい花でも、花粉が多く落ちる種類は管理が難しく、清潔感に欠ける印象を与えてしまいます。特にユリは人気の供花ですが、花粉が衣服や白木位牌、仏具につくと落ちにくく、見た目にも良くありません。
-
注意点:ユリを使う場合は、あらかじめ花粉を取り除いたものを使用するのが一般的です。
-
代替案:花粉の少ないトルコキキョウやアルストロメリアなど、管理がしやすく美しい花材がおすすめです。
【関連記事】ペットのお供え花にふさわしい種類は?おすすめの色や選び方をご紹介
お供え花の色・本数・飾り方の基本マナー
供花は「花の種類」だけでなく、色合いや本数、飾り方によっても大きく印象が変わります。マナーを守った美しい供花は、故人への敬意とご遺族への思いやりを形にする大切な要素です。

お供え花の色の選び方
-
初七日〜四十九日(忌明け前):
基本は白一色。清浄・追悼の意味を込めて、白い花のみでまとめるのが一般的です。 -
四十九日以降(年忌法要・命日など):
淡いピンク・薄紫・クリームイエローなどのやさしい色味を加えても差し支えありません。明るすぎる色や原色は避け、落ち着いたトーンで統一するのがポイントです。 -
お盆・お彼岸など季節の行事:
紫や黄色、青などの「季節感を感じる色」も加えてよいとされています。お盆では「迎え火」「送り火」の意味から、やや明るめの色を使うこともあります。
お供え花の本数のマナー
お供えの花束として選ぶ場合は本数にも気を遣う必要があります。以下の点を抑えておきましょう。
-
奇数(3本・5本・7本)を基本に
仏教では「奇数」が縁起が良いとされており、供花の本数は奇数が基本です。特に5本や7本は見た目のバランスもよく、アレンジしやすい本数です。 -
偶数は避ける
偶数は「割り切れる=縁が切れる」と連想されるため、供花では避けた方が良いとされています。特に2本、4本などはNGとされることが多いです。
お供え花の飾り方のポイント
-
仏壇の場合
基本は左右対称に一対で飾るのが正式です。片方だけではなく、両側に均等なボリュームで供えると整った印象になります。花器の高さや位置も揃えるようにしましょう。 -
お墓の場合
花筒に左右対称に挿すのが一般的です。花の高さを揃え、向きも整えることで故人への敬意が伝わります。季節の風や陽射しによって花が傾きやすいので、しっかりと固定する工夫も必要です。 -
ご家庭で飾る場合
コンパクトなアレンジメントでも、整ったシルエットと落ち着いた色調を心がけましょう。飾る場所の雰囲気(遺影・仏壇・写真立ての周りなど)に合わせて高さや花器を選ぶのもポイントです。
お供え花の用途別・シーン別におすすめのお花
供花は、贈るタイミングやシーンによって選び方やマナーが異なります。ここでは代表的な場面ごとに、ふさわしい花のスタイルや注意点をご紹介します。

枕花(まくらばな)・通夜の供花
故人が息を引き取った直後から通夜までの間に、枕元に供える花
枕花は、急な訃報を受けていち早く駆けつける親族やごく親しい友人が贈る供花です。故人の眠りを静かに見守るような、落ち着いた雰囲気のアレンジメントが選ばれます。
-
色合い:白を基調に、淡いピンクや紫をわずかに加える程度が一般的。派手すぎる色は避けます。
-
スタイル:卓上サイズのコンパクトなアレンジや花束。縦長や横長のアレンジメントも人気です。
-
贈る相手:親族、親しい友人、付き合いの深い職場関係者など。
-
おすすめの花:白ユリ、スプレーマム、カーネーション、トルコキキョウなど。
通夜の場にもそのまま飾られることが多いため、持ち運びやすさや清潔感も重視されます。
葬儀・告別式の供花
故人を送る最も正式な場で飾られる、祭壇周囲の供花
通夜から翌日の葬儀・告別式では、祭壇の左右に大きく目立つスタンド型の供花を贈るのが一般的です。主に会社関係や団体、友人一同など、少し距離のある立場からの供花が中心となります。
-
色合い:白一色、または淡い紫やグリーンを加えた上品なトーンが主流。
-
スタイル:スタンドタイプ(1段または2段)、または式場の形式に合わせた装花。
-
贈る相手:企業・団体、友人グループ、恩師・教え子など。個人でも贈ることが可能です。
-
おすすめの花:胡蝶蘭、ユリ、菊(輪菊・スプレー菊)、デルフィニウム、リンドウなど。
式場に直接届けるため、事前に葬儀会社や式場との連携が必要です。名札の記載内容や配置の順番もマナーに関わります。
【供花】白色・グリーンのお供えアレンジメント 10,000円 シンプルで清らか。命日や法要にふさわしい落ち着いた美しさのお供えアレンジメント
¥11,000
法要・法事(四十九日・一周忌・三回忌など)
節目の供養の場で、ご遺族が静かに故人を偲ぶ時間
四十九日(忌明け)や一周忌・三回忌などの法要では、落ち着きと温かみを感じる組み合わせが好まれます。仏壇や会食の場に飾るため、大きすぎず控えめなサイズ感がポイントです。
-
色合い:白をベースに、淡いピンクや黄色、紫を加えて柔らかく。忌明け以降は明るさを少し加えてもOK。
-
スタイル:一対のアレンジメント、または花束スタイルが人気です。
-
贈る相手:親戚、ご近所、故人の恩人や友人など。施主自身が用意することも多いです。
-
おすすめの花:カーネーション、トルコキキョウ、アルストロメリア、スターチス、ケイトウなど。
自宅での法要では仏壇との調和を意識し、高さ・色・香りのバランスに配慮するとより丁寧です。
お墓参りの供花
屋外のお墓に手向ける、季節の節目や命日での花
お墓参りでは、雨風や直射日光に耐えられる、耐久性のある花材と構造が求められます。墓前に飾った際に倒れにくいよう、丈が短めで茎のしっかりした花が好まれます。
-
色合い:落ち着いた白・紫・青系が中心。季節に応じたやさしい色も可。
-
スタイル:左右対称の花束(仏花スタイル)が基本。対になる一対で用意します。
-
おすすめの花:リンドウ、菊、トルコキキョウ、スターチス、デンファレなど。
花筒に入れる際は、茎をしっかりカットして水の吸い上げを良くすることも大切です。香りが強すぎる花や花粉が多い品種は避けましょう。
お供え花の贈り方・注文時のマナーと注意点
供花を贈るときは、「心を込めて贈る」という気持ちだけでなく、相手に負担をかけない丁寧な手配とマナーに沿った形式も大切です。

手配のタイミング
-
枕花・通夜・葬儀の場合:できれば通夜の前日までに手配し、式場へ時間指定で届けましょう。
-
法要・命日など家庭用の場合:前日~当日の午前中までに到着するよう調整をしましょう。
直前の注文では間に合わないこともあるため、余裕をもって依頼するのが基本です。
伝えるべき情報(花屋に依頼する際)
-
贈る用途(通夜・葬儀・法要・お盆など)
-
贈り主の関係性(親族・会社・友人など)
-
希望するスタイルや色味(白を中心/一対で等)
お供え花の名札の書き方とマナー
供花には名札を添えるのが一般的です。表記はシンプルに、贈り主の立場をわかりやすく記載しましょう。
-
【例】「○○株式会社」「○○課 一同」「故人の友人 ○○より」「○○家親族一同」など
-
個人名を出す場合は、フルネームで記載するのが正式です。
配送マナー・配慮すべき点
-
届け先の都合(在宅状況、式場の指定受付時間)を必ず確認する
-
メッセージカードを添える場合は、過度に個人的・宗教的な表現は避ける
-
配達時の時間帯指定や取扱注意の指示なども忘れずに行いましょう
お供え花に関するよくある質問Q&A
Q. お供え花はいつ届けるのが理想ですか?
A. 通夜や葬儀の場合は、前日または当日の式が始まる前に届くよう手配するのがマナーです。法要では前日までに届くようにしましょう。
Q. プリザーブドフラワーや造花でも問題ありませんか?
A. 原則としては生花が望ましいですが、状況や環境によってはプリザーブドフラワーや造花でも失礼にはあたりません。特に高温多湿な季節や高齢者の自宅では、手入れのしやすさの観点から生花以外を選ぶことが増えています。
Q. 会社から供花を贈る場合、どのような形式がよいですか?
A. 一般的には「大きめのアレンジメント」「スタンド花(1段または2段)」が選ばれます。「○○株式会社 一同」と名札を添えて、式場に直接手配するのが基本です。
まとめ|お供え花に心を込めて、故人への想いを伝える

供花は、故人への哀悼や感謝の気持ちを伝えるための、深い意味を持った贈り物です。どのような場面で、どんな花を選ぶかによって、その想いの伝わり方も変わってきます。色合いや本数、飾り方、贈るタイミングやマナーなどに気を配ることで、相手への心遣いがより一層伝わります。
大切なのは、形式にとらわれすぎず、故人を思う気持ちを大切にすることです。花に込めたやさしい想いが、ご遺族の心にもそっと寄り添い、あたたかな記憶として残ることでしょう。