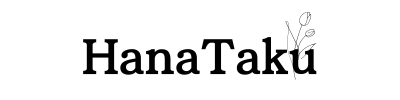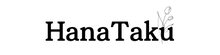お盆の季節になると、仏壇や精霊棚に欠かせない花として「ほおずき」を目にすることが増えます。独特の形と鮮やかな橙色が印象的なこの花は、見た目の美しさだけでなく、故人や先祖への祈りが込められた特別な意味を持っています。本記事では、ほおずきがお盆に用いられる理由や飾り方、他の供花との組み合わせ、マナーや注意点まで解説します。
お盆に飾る「ほおずき」の意味とは?

| 科名/属名 | ナス科/ホオズキ属 |
| 和名 | ホオズキ(鬼灯、酸漿) |
ほおずき(鬼灯)は、その形状と色から「提灯(ちょうちん)」に見立てられています。お盆には故人やご先祖の霊がこの世に帰ってくると考えられており、ほおずきはその霊が迷わず戻ってこられるよう、灯りとして飾られます。
また、赤橙色の鮮やかな色は魔除けの意味もあるとされ、家族を守るための祈りも込められています。中に空洞のある実の構造も「魂が宿る器」としての象徴と見なされることもあります。
【関連記事】お盆のお供えする花の種類は?12種類のおすすめをご紹介
ほおずきはどんな場面で使う?お供えのシーン別解説
朱色のふっくらとした灯りのような実が特徴の「ほおずき(鬼灯)」は、夏のお盆時期に欠かせない存在です。ここではほおずきがどのような場面で使われているのかを、精霊棚・仏壇・お墓参り・室内装飾など、シーンごとにご紹介していきます。

精霊棚や仏壇へのお供え
お盆の行事の中で特に重要なのが、ご先祖様の霊をお迎えするために設置される「精霊棚(しょうりょうだな)」です。これは仏壇とは別に設けられる特別な祭壇で、期間中は果物や野菜、季節の花々とともに、ほおずきも丁寧に供えられます。
ほおずきはその独特な形状と色から、迎え火・送り火の象徴としての役割を担っており、左右対称に飾ることで「霊を迷わせない」ともいわれています。精霊棚に吊るしたり、竹かごに入れて置いたりするスタイルが一般的で、見た目にも美しく、儀式的な意味合いも持ちます。
また、仏壇へのお供えとしても人気が高く、花瓶に他の供花と一緒に挿したり、小さな盆花アレンジの中に組み込んだりすることで、よりお盆らしい趣のある飾りになります。ほおずきの橙色は華やかすぎず、落ち着いた彩りで仏前を清らかに彩ってくれます。
お墓参りでの使用
お盆の時期はお墓参りも欠かせません。このときにも、ほおずきは供花のひとつとして選ばれることが増えています。
特に近年では、暑い時期でも長時間美しさを保てるように、水に強い品種や造花タイプのほおずきを選ぶ方も多くなっています。
ほおずきを単体で供えるだけでなく、リンドウや菊、カーネーションなどの定番供花と組み合わせて花筒に生けることで、故人を偲ぶ華やかなお墓飾りになります。また、故人が好きだった色合いや花と組み合わせてオリジナルのアレンジをするのも素敵な供養の形です。
お盆の室内装飾として
近年では、お盆のしつらえを「インテリアとしても楽しむ」という家庭が増えてきています。その中で、ほおずきは季節感のあるアイテムとして非常に人気があります。
ドライに加工されたほおずきをリースやスワッグ(壁掛け飾り)に取り入れたり、生花のアレンジメントの中に加えたりと、その用途は多岐にわたります。ほおずきは空間に柔らかい暖色のアクセントを加え、飾るだけで季節感と落ち着いた雰囲気を演出します。
特に都市部では、仏壇のない家庭や核家族が増えたことから、形式にとらわれない「想いを込めた供養」として、ほおずきを使ったアレンジメントやプリザーブドフラワーの贈り物などが注目を集めています。
【商品一覧】お盆に贈るお供え花
【供花】白色・黄色・オレンジ色のお供えアレンジメント 5,000円 感謝と祈りを明るく彩る、定番サイズのお供えアレンジメント ¥5,500
ほおずきを取り入れたお盆用のお供え花の組み合わせ例

ほおずきはその提灯のような形と温かみのある橙色が、どこか懐かしく、日本の夏やお盆らしさを感じさせてくれる花材です。単体でも存在感のある植物ですが、他の伝統的な供花と組み合わせることで、さらに豊かな意味合いや美しさを持たせることができます。
特に以下のような花との組み合わせは、調和のとれた印象を与え、お供え花としてふさわしい仕上がりになります。
-
菊(白・黄):仏花の代表格である菊は、清廉さや高貴さを象徴し、お盆には欠かせない存在です。白は「純粋な心」、黄色は「敬意」を表すとされ、ほおずきの橙と組み合わせると、全体に落ち着いた優しい色調になります。
-
リンドウ(紫):リンドウは秋の花として知られていますが、地域によっては夏から出回ることもあります。紫は「誠実さ」や「尊敬」の象徴です。ほおずきと並べると、大人びた上品さが際立ちます。
-
ミソハギ:お盆の精霊棚に欠かせない植物で、水辺を好み、古くから「精霊花」として重宝されてきました。水に浸して使うことが多く、ほおずきと並べることでよりお盆の儀式的な意味合いが強まります。
-
スターチス:色とりどりの小さな花が密集しており、アレンジにボリューム感を出したいときに便利です。乾燥にも強く、長持ちするのも魅力の一つで、ほおずきの橙色とのバランスも取りやすいです。
-
カーネーション(淡いピンク・白):やさしさや感謝の気持ちを表す花として、仏花の中でも近年人気が高まっています。ピンクや白の柔らかい色合いが、ほおずきの鮮やかさを穏やかに引き立てます。
色の選び方としては、全体的に派手になりすぎないよう「白・紫・橙・淡いピンク」などを基調にまとめるのがおすすめです。色の数が多すぎると散漫な印象になるため、3色程度に絞って構成するのが調和を保つポイントです。
【関連記事】お盆に飾るミソハギの花の意味と飾り方|供花としてのマナーと使い方ガイド
【商品一覧】新盆・初盆に贈るお供え花
ほおずきの選び方と管理方法
ほおずきには、生花として流通するフレッシュな状態のものからドライフラワー、リアルな質感を再現した造花まで様々なタイプがあります。使用するシーンや飾る場所によって最適な種類を選ぶことで、より長く楽しむことができます。

生花のほおずき
自然な色合いを楽しめるのが生花のほおずきです。お盆の定番である菊やトルコキキョウなどのお花と組み合わせると、
ただし、夏場は高温多湿になりやすく、管理には十分な注意が必要です。水替えは毎日行い、直射日光やエアコンの風が直接当たらない場所に飾るようにしましょう。花瓶に飾る場合は、茎の切り口を斜めにカットして水の吸い上げを良くするなどの工夫も有効です。
ドライフラワーのほおずき
乾燥させたほおずきは、色がやや落ち着いたトーンになり、自然なアンティーク感が魅力です。長期間飾ることができ、風情ある雰囲気を醸し出してくれます。精霊棚や仏壇の飾り、あるいはリースや盆花アレンジメントの素材としても活躍します。
造花のほおずき
最近ではまるで生花のような造花が増えており、暑いお盆の時期には造花のほおずきも人気があります。お水の管理の手間がかからないため、お墓参り用や室内装飾用としておすすめです。
お墓や屋外に飾る場合は、耐久性の高い素材(ポリエステル、ポリエチレン)製のものを選ぶと、雨や風でも型崩れしにくくおすすめです。
【供花】白色・グリーンのお供えアレンジメント 5,000円 シンプルで清らかな定番サイズのお供えアレンジメント
¥5,500
ほおずきの購入時期と価格帯の目安
ほおずきは主にお盆の時期に出回り、その時期は地域によって異なります。だいたい毎年7月上旬から8月中旬にかけて全国の市場や店舗に出回ります。購入できる場所や価格の目安は以下を参考にしてみてください。
主な購入先
-
花屋(生花やアレンジ商品)
-
スーパー・青果店(枝付きや束売り)
-
ホームセンター
-
インターネット通販(全国配送可・ギフト対応)
価格帯の目安
| 種類 | 価格帯 |
|---|---|
| 1本売り | 300円~500円前後 |
| 房付きの束(5~10本) | 1,000円~3,000円程度 |
| アレンジメント込みのギフト | 3,000円~5,000円程度 |
通販での購入は便利ですが、生花の場合は鮮度や梱包状態に配慮する必要があります。不安がある場合は、近隣の花屋やレビューを確認の上、利用しましょう。
ほおずきを飾るときの注意点とマナー

お供えとしてほおずきを使う際には、以下のようなマナーや注意点を守ると、より気持ちのこもった飾り方ができます。
-
数は奇数が基本:仏事では縁起の良いとされる奇数(3本・5本など)で飾るのが一般的です。
-
左右対称に飾る:精霊棚や仏壇では、対になるように左右に配置することで、整った印象を与えます。
-
高温多湿を避ける:特に生花のほおずきは暑さで萎れやすいため、涼しい場所に飾る工夫が必要です。
-
派手すぎない配色にする:仏花は落ち着いた色味が基本。ほおずきの赤オレンジ色を軸に、白や紫などの寒色系を組み合わせると上品です。
-
単独よりも他の花と組み合わせる:他の供花と組み合わせることで、見た目に奥行きと意味合いが生まれます。
また、贈り物としてほおずき入りの供花を届ける際には、ラッピングや立て札、メッセージカードにも配慮することで、受け取った側に気持ちが伝わりやすくなります。
【供花】白色・ピンク色のお供えアレンジメント 15,000円 柔らかな色合いで偲ぶ、圧倒的な存在感と美しさで祈るお供えアレンジメント ¥16,500
よくある質問(Q&A)
Q. ほおずきだけを飾っても大丈夫?
A. 問題ありません。ただし、全体の印象が寂しく感じられることもあるため、他の花と組み合わせて飾るとより華やかで整った印象になります。
Q. どこに飾るのが正解?
A. 精霊棚の左右や、仏壇の手前に飾るのが一般的です。お墓参りで使う場合は、花筒に挿したり墓前の供物台に置く方法があります。
Q. お盆が終わった後、ほおずきはどう処分すればいい?
A. 生花の場合は新聞紙などで包み、一般ゴミまたは可燃ゴミとして処分します。ドライフラワーや造花の場合は、次年に持ち越すか、お焚き上げを依頼する方法もあります。
まとめ|ほおずきに込めた祈りを大切に
飾る目的や場所に応じて、生花・ドライフラワー・造花を使い分けたり、他の花と調和させたりすることで、より思いのこもったお供えが可能になります。
今年のお盆には、ぜひ「ほおずき」を取り入れて、静かに心を寄せるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。