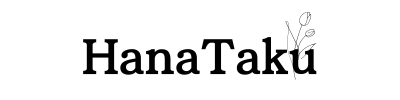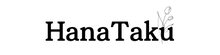お盆に飾る供花の中でも、神聖なイメージを持つ「蓮の花」は特別な存在です。極楽浄土に咲くとされるこの花は、故人への祈りや感謝の気持ちを込めて供えるにふさわしい花として親しまれてきました。
この記事では、蓮の花の意味や由来、仏壇やお墓での飾り方、生花が手に入りにくい場合の代用品、他の花とのアレンジやマナーまで解説します。
蓮の花とは?特徴と基本情報

| 科名/属名 | ハス科ハス属 |
| 和名 | 蓮 |
蓮(はす)は、池や沼地など水辺に咲く多年草で、大ぶりの花と円形の大きな葉が特徴です。花の色は白や淡いピンクが多く、朝に開いて午後には閉じるという独特のリズムを持ち、静けさや神聖さを感じさせてくれます。
開花時期は6月から8月にかけて。ちょうどお盆の時期と重なることから、供花としても長年親しまれてきました。花だけでなく「蓮の葉」「蓮の実」にも意味があり、仏具や供物として活用されることもあります。
また、蓮の花は香りが控えめで清らかさを連想させるため、弔事の場面にふさわしい花とされています。
【商品一覧】お盆に贈るお供え花
なぜお盆に蓮の花を飾るのか?意味と由来
お盆は、日本の伝統的な行事のひとつであり、故人やご先祖様の霊を迎え、感謝と供養の気持ちを捧げる期間です。この時期に蓮の花を供えることには、深い意味と由来があります。
蓮は、仏教において「清浄」「悟り」「再生」を象徴するお花です。泥の中で根を張りながらも、その濁りに染まることなく美しく咲く姿は、「心の清らかさ」や「魂の浄化」の象徴とされてきました。そのため、故人の魂が穢れから解き放たれ、極楽浄土へと導かれるよう願いを込めて、蓮をお供えする習慣が生まれたのです。
また、「輪廻(りんね)」という言葉にも象徴されるように、命のつながりや再生を表現する花として、蓮は単なる供花を超えた“精神性”を帯びた存在として扱われます。
商品:商品1
蓮の花の供え方・飾り方|仏壇・お墓・精霊棚
仏壇に供える場合
蓮の花を1本、もしくは3本など奇数で飾るのが一般的です。左右対称に配置することで整った印象になります。茎が長い場合は花瓶の高さに合わせてカットし、安定感をもたせるようにしましょう。
スペースが限られている場合は、蓮の葉や実を使ったコンパクトな供え方も可能です。最近ではミニサイズの蓮の造花やプリザーブドフラワーも出回っており、小型の仏壇にもしっくり収まるアレンジができます。
精霊棚(しょうりょうだな)での使い方
お盆に設ける精霊棚では、蓮の花は中心またはお供え物の周辺に配置されることが多いです。ほおずきや季節の果物、茄子や胡瓜で作った精霊馬(しょうりょううま)と一緒に飾ることで、視覚的にもお盆らしさが際立ちます。
花器はガラス製や竹製など涼しげなものを選ぶと、夏の暑さの中でも清涼感を演出できます。また、蓮の葉を敷いてその上に供物を置く飾り方も、見た目に上品でおすすめです。
お墓に供える際の注意点
お墓への供花として蓮を使用する際には、日差しや風に配慮が必要です。蓮はもともと水中植物であるため、切り花にするとやや傷みやすい特徴があります。水をたっぷり含ませた花筒を使用し、日差しの強い時間帯を避けてお参りするのが理想です。
また、茎が長くて倒れやすい場合には、短く切って花筒の深さに合わせるか、他の花と組み合わせて安定させるようにしましょう。
【供花】白色・黄色・オレンジ色のお供えアレンジメント 3,000円 感謝と祈りを明るく彩る、小さめサイズのお供えアレンジメント ¥3,000
生花の蓮は手に入りにくい?蓮の代用・加工品について

蓮の花は生花としての流通量が多くないため、時期や地域によっては入手が難しいことがあります。その場合は、以下のような代用品がよく使われています:
-
造花(アートフラワー):最近では非常に精巧な造花が多く、見た目にも自然で違和感のないものが手に入ります。
-
プリザーブドフラワー:加工により長持ちするため、夏場の仏壇やお墓にも適しています。
-
蓮の葉や蓮の実:蓮を象徴する素材として、花が手に入らない場合でも十分に雰囲気が伝わります。
また、蓮の花を模した「蓮型キャンドル」や「蓮形の陶器・ガラス花器」など、間接的に蓮を表すアイテムを取り入れる方法もあります。
他の供花との組み合わせ方|蓮を引き立てる花とは
蓮は存在感のある大きな花なので、他の花とのバランスを考えることが大切です。以下のような組み合わせがお盆らしい雰囲気となります。
| 花の種類 | 意味・役割 | 蓮との相性 |
|---|---|---|
| 白菊・小菊 | 清らかさ・哀悼の意 | 落ち着いた調和が取れる |
| リンドウ | 誠実・悲しみを乗り越える象徴 | 紫の色味が蓮の淡色を引き立てる |
| ほおずき | 霊を導く提灯の象徴 | 差し色として華やかさをプラス |
| カスミソウ・スターチス | 軽やかさ・日持ちの良さ | ボリュームと立体感を出す効果 |
配置の際は、蓮を中心に据え、他の花で高さや横幅のバランスを取るよう心がけましょう。仏壇が小さい場合は、小菊やリンドウなどと数本でまとめてコンパクトに仕上げるのもおすすめです。
【関連記事】お盆に飾るミソハギの花の意味と飾り方|供花としてのマナーと使い方ガイド
【関連記事】お盆のお供えする花の種類は?12種類のおすすめをご紹介
蓮の花を飾る際のマナーと注意点

蓮を供花として取り入れる際には、以下のようなマナーや配慮が求められます:
-
奇数本で供える:縁起の良い本数として、1本・3本・5本が一般的です。
-
派手すぎない色味を選ぶ:白や淡いピンクが基本。あくまで落ち着いた雰囲気を大切に。
-
仏壇や墓前に合ったサイズを選ぶ:大きすぎると他の供花や仏具と干渉するため、空間とのバランスを考えましょう。
-
こまめな水管理をする:暑い時期は特に花が傷みやすいため、朝晩の水替えや水切りを行うのが理想です。
-
地域の慣習に合わせる:蓮の花を供える風習がない地域もあるため、事前に確認すると安心です。
心を込めた花であるからこそ、マナーを守り、故人や遺族に配慮した供え方を意識しましょう。
【商品一覧】新盆・初盆に贈るお供え花
よくある質問Q&A
Q. 蓮の花は必ず生花でなければなりませんか?
A. いいえ、生花にこだわる必要はありません。造花やプリザーブドフラワーなど、現代のライフスタイルに合った供花の選び方も広く受け入れられています。
Q. 蓮の葉や実だけでも供えてよい?
A. はい、蓮の葉や実にも蓮の象徴的な意味があり、十分に供花としての役割を果たします。特に暑さで生花が持たない場合などにおすすめです。
Q. 地域によって蓮を供えないところもありますか?
A. あります。地域や宗派によって供花の種類は異なり、蓮を用いない風習の場所もあります。地元のしきたりや家族の意向に合わせて選ぶことが大切です。
【供花】白色・ピンク色のお供え花束 3,000円 柔らかな色合いで偲ぶ、小さめサイズのお供え花束 ¥3,300
まとめ|用途に合わせて蓮を選ぼう

蓮の花は、お盆における供花として非常に象徴的な存在です。泥の中から気高く咲くその姿に、私たちは清らかな心や故人への祈りを重ねます。
生花にこだわらず、造花や蓮の葉、実なども上手に取り入れながら、家庭や地域に合った形で蓮を供えることが、今の時代に合ったお盆の過ごし方とも言えます。
お盆の時期に生花を見つけたら、ぜひ飾ってみてください。