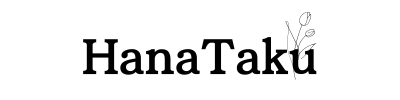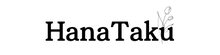故人を偲び、想いを込めて贈るお供え花。しかし、「どんな花が適切?」「この色は失礼に当たらない?」と迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、お供え花を贈る際に気をつけたいマナーやタブー、花の選び方、色の意味、場面ごとの注意点まで解説します。
お供え花とは?その意味と役割

お供え花(供花)とは、亡くなった方への哀悼の意、感謝、敬意などを込めて捧げる花のことを指します。通夜・葬儀・告別式・法要・命日・お盆・お彼岸など、さまざまな仏事や弔事で供えられます。
花の種類や大きさ、形式は、宗教や地域の慣習、供える場所(仏壇・式場・墓前など)によって異なりますが、最も重要なのは「故人やご遺族への配慮」です。供花はただ飾るためのものではなく、故人を偲び、周囲の人の心に寄り添うための手段です。
また、供花には空間を清らかに整える役割もあります。法事の際、参列者や遺族が落ち着いて手を合わせられるよう、場の空気を整える一助となります。
現代では形式に縛られすぎず、故人との関係や想いを表現した花選びも重視されています。タブーとされていたとしても生前に故人が好きだった花を選ぶ、季節感を取り入れるなど、個別の配慮を反映させることも一般的です。
そして、供花にメッセージカードを添えたり、宅配サービスで直接届けるケースも増えています。供花を選ぶ際には、「供えるタイミング」「飾る場所」「花の管理のしやすさ」など、実用的な観点も忘れずに確認しておくと安心です。
お供え花の適した色マナー・タブー
お供え花の色選びは、場の雰囲気を左右する重要なポイントです。色にはそれぞれ意味やイメージがあり、特に弔事の場では相応しい配色を選ぶことが求められます。

白は基本の色
通夜や葬儀の際は、最も一般的で無難なのが「白」を基調とした花です。白色は「清浄」「純粋」「静寂」などの意味を持ち、故人への敬意や哀悼の気持ちを真っ直ぐに伝えられます。
どの宗教・宗派でも広く受け入れられており、場を清らかに整える効果もあるため、まず白を選んでおけば安心です。
組み合わせるなら淡い色
通夜・葬儀の初期段階では白が基本ですが、四十九日忌以降の法要や命日、あるいは自宅での供養の場面では、淡い色味の花を加えても問題ありません。具体的には、薄いピンクや薄紫、クリーム色、薄い水色などが挙げられます。
これらの色は落ち着いた印象を保ちつつ、柔らかさや優しさを演出します。派手さを避け、空間に溶け込むような色合いを心がけることがポイントです。
避けたい色
赤やオレンジ、鮮やかな黄色など、強い色彩は祝い事や明るいイベントを連想させるため、弔いの場では避けられる傾向があります。特に真紅は結婚式やお祝いの象徴色として認識されやすいため注意が必要です。
ネオンカラーや蛍光色も派手すぎて場違いとなるため、選ばないようにしましょう。
故人の好きだった色を取り入れるには
故人が生前に特定の色や花を好んでいた場合、その色を取り入れたいと思う方もいます。こうした場合は、全体の雰囲気を壊さない範囲で、ワンポイントとして色を加えるのが望ましいです。例えば淡いトーンに抑えたり、小さなアクセントとして用いるなど工夫すれば、マナー違反とは見なされにくくなります。遺族の気持ちや故人の人柄を尊重する意味でも効果的です。
シーン別|お供え花の選び方とマナー
お供え花は弔いの場面ごとに適切な種類や形、色、サイズが異なります。ここでは代表的なシーンごとにポイントを整理します。

通夜・葬儀
故人の逝去直後に行われる通夜や葬儀の場では、白を基調にした落ち着いた花が一般的です。個人が贈る場合は、枕元に置く「枕花(まくらばな)」という小さなアレンジメントが中心です。
会社や団体として贈る際は、大きなスタンド花を式場に直接届けることが多く、名札を添えて贈り主の名前や関係を明示するのがマナーです。事前に葬儀社に確認し、宗派や地域の慣習を尊重した選び方をしましょう。
法要(四十九日・一周忌・三回忌など)
四十九日忌までは白を中心としたシンプルな花が望まれますが、一周忌や三回忌以降は淡い色を加えても問題ありません。自宅や寺院での法要には、5,000円~10,000円サイズの花束やアレンジメントが適しており、仏壇や床の間に飾りやすいサイズ感が好まれます。
お花の種類としては日持ちのよい菊やリンドウ、トルコキキョウ、スターチスなどがよく選ばれます。花の色や種類を通じて故人の人柄や好みを反映させると、より丁寧な印象になります。
命日・月命日
毎月の命日や月命日のお参りでは、小ぶりで管理しやすい花束や日持ちする花が好まれます。最近では忙しい方でも手軽に供えられるよう、生花を加工したプリザーブドフラワーを利用するケースも増えています。これらは生花に比べて長持ちし、手入れが簡単なため、現代の供花の選択肢として人気です。
お盆・お彼岸
お盆やお彼岸は季節の節目であり、多くの人が墓前や仏壇に花を供えます。この際は季節感を反映した花を選び、できるだけ長く飾れるよう日持ちの良い品種を選ぶことが重要です。
お盆や秋のお彼岸では菊、リンドウ、スターチスが代表的で、色は白、紫、淡い黄など落ち着いたトーンが選ばれることが多いです。お墓参りの場合は風や暑さに強い丈夫な花を選ぶと、より安心して供えられます。
【関連記事】お供え花のメッセージカードの例文・書き方・マナーをご紹介します
用途別・シーン別におすすめの供花

枕花(まくらばな)
枕花は、亡くなった直後に故人の枕元に供える花で、通夜や葬儀の前に届けられます。主に一報を受けた親族やごく親しい友人が用意するもので、白を基調としたコンパクトなアレンジメントが一般的です。大きさは控えめにし、香りの強くない花を中心に構成することで、故人を静かに偲ぶ空間を作ります。
枕花の手配は、急な対応が必要となるため、地域の花店や葬儀社を通じて迅速に準備するのが基本です。また、名前札(送り主名)を添える場合は、通夜前までに確実に届くように手配します。
葬儀・告別式用の供花
葬儀・告別式の供花は、祭壇の左右に飾られる大型のスタンド花が一般的です。会社関係者や親戚、親しい知人など、幅広い立場の人が贈るため、花の大きさや本数にある程度のボリュームが求められます。
色は白を基調としつつ、淡い紫やピンクなど落ち着いた色味を差し色として取り入れるケースも増えています。スタンド花には必ず「名札(供花札)」を付け、贈り主の名前と立場(○○株式会社 代表取締役 ○○など)を明示するのがマナーです。
供花を贈る際には、事前に葬儀社や遺族へ確認を取り、「供花を受け付けているか」「どの葬儀社に依頼するべきか」などを把握しておく必要があります。宗派や地域によってはスタンド花が好まれない場合もあるため、確認を怠らないようにしましょう。
法要(四十九日・一周忌・三回忌など)
仏教の年忌法要には、それぞれふさわしい供花があります。
-
四十九日(忌明け):この節目までは、白を基調とした供花が基本。式の厳粛さに合わせた落ち着いた花選びが求められます。
-
一周忌以降:淡い色(淡ピンク、淡紫、クリーム色)を加えたアレンジが許容されるようになります。一周忌では穏やかな色合い、三回忌以降は季節感を取り入れつつも抑えめを意識しましょう。
自宅での法要では飾りスペースが限られるため、中型のアレンジメントや花束タイプ(仏花)が適しています。故人の趣味や好みに合った花を選ぶことも、丁寧な弔いの姿勢を表します。
命日・月命日
毎月の命日や年忌の節目には、負担にならないサイズと日持ち重視が鍵です。
-
小さな花束:白や淡い色を中心に、花瓶で数日間飾れる程度のボリュームが最適。飾る方の手間を減らせます。
-
プリザーブドフラワー:長く美しい状態を保つため、忙しい方や遠方からの供花に重宝されます。香りや花粉を気にせず飾れる点もメリットです。
お盆・お彼岸
季節に応じた供花選びが必要です。
-
花材の選定:菊(白・淡黄)、リンドウ(紫)、スターチス(白・淡紫)などが定番。
-
耐久性も重視:暑さや風に強い花材を選ぶことで、お盆期間中の供花を安心して保ちやすくなります。
-
色づかい:白・紫・淡黄の落ち着いた色調は、供養の場にふさわしい雰囲気を保ちます。赤やビビッドな色は避けましょう。
用途・場面別おすすめ供花
| シーン | 花材例 | ポイント |
|---|---|---|
| 枕花・通夜 | 白菊、カーネーション、スターチス | 白基調、花粉や香り控えめ |
| 葬儀・告別式 | 白・淡色の大型アレンジ、名札付き | 式場に映える存在感、周囲との調和を意識 |
| 法要 | 白・淡色のお花 | 仏壇や祭壇に収まるサイズ |
| 命日・月命日 | 小さめの花束、プリザーブドフラワー | 管理の手間が少ないものを選ぶ |
| お盆・お彼岸 | 菊・リンドウ・スターチス・季節のお花を選択 | 季節感と日持ちのバランス |
贈り方の基本とマナー
供花を贈る際には押さえておきたいマナーをご紹介します。
-
贈り先を確認:葬儀場・ご遺族のご自宅・お寺など、届け先を事前に把握します。式場は受付を通して届けるケースが一般的です。
-
立札:「御仏前」「御供」など、形式に合わせた表記を選びます。
-
個人名 + 連名:会社・団体では代表者名+「一同」など。
-
冠文字に関しては、宗派・地域により用語差があるため事前確認すると安心です。
-
-
配送日時の指定:通夜・葬儀なら前日までに、法要なら当日朝までに着くよう手配します。基本的には前日までにお届けすると安心です。
-
ボリュームと花材の選定:小規模な式場なら中小型、大型斎場なら大きなスタンド花など。会場に合わせた適切なサイズ選びがポイントです。
-
事前連絡の重要性:遺族や葬儀社に一言伝えておくことで、受け取りミスや混乱を防げます。
【関連記事】お供え花に添える立て札の例・書き方|連名の場合はどうする?
よくある質問Q&A
Q. 通夜と葬儀の両方に同じお供え花で問題ないでしょうか?
問題はありませんが、葬儀式場は供花が多いため、初めての方は3,000円~10,000円程度のサイズが適切です。
Q. お供え花としてプリザーブドフラワーを贈ってもよいでしょうか?
香りや花粉の心配がなく、手間も少ないため、命日など繰り返し使う場面での利用がおすすめです。
Q. 故人の好きな赤い花を少し入れたいのですが、問題ないでしょうか?
赤を含む場合は「ワンポイント」で抑えるのが望ましく、全体が祝賀的にならないよう注意してください。
Q. お供え花を贈る際、宗教を配慮した色選びはどうすればよいでしょうか?
白に加えて淡色が一般的で、宗派問わず使える配色です。園芸花よりも菊やカーネーション、スターチスなどが無難です。
実用的なチェックリスト
お供え花を贈る際の要点を整理してチェックリストにしました。
-
花の色:白・淡色(淡ピンク・紫・クリーム・淡黄など)
-
花材:トゲ・毒性・強香・ツル性は避ける
-
サイズ:場に応じた大きさを選ぶ
-
香り・花粉:控えめ・少ないものを選ぶ
-
包装:名札・表書き・保水と梱包状況をチェック
-
配送日:通夜・葬儀なら前日/法要なら当日午前中
-
事前連絡:遺族または葬儀社にお知らせする
まとめ|お供え花のマナー・タブーをしっかり理解しよう

お供え花は、故人への思いとご遺族への配慮を形にする手段です。色、花材、サイズ、香り、花粉など、それぞれが適切に選ぶことで、供花としての意味を損なわずに、心を届けることができます。
悩む場合には白基調のお花を選び、花屋さんで注文する場合はスタッフの方に相談することをおすすめします。