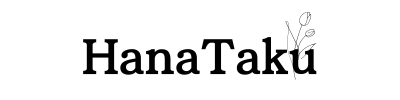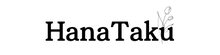四十九日や年忌法要などの法事の際、本堂にお供えする花束には、故人への敬意と感謝の気持ちを込めて心を込めて選びたいものです。特に一対(二束)の花束は、仏教における供養の基本形とされており、格式ある本堂でも失礼のない形とされています。
この記事では、本堂に持参する花束の相場感や選び方のマナーについて、分かりやすくご紹介します。スタンド花や豪華なアレンジメントではなく、手渡しできる対の花束を想定した内容ですので、個人として参列する際の参考にしていただけます。
本堂に供える花束の相場はいくら?

個人で持参する場合の一般的な相場
法事の際、本堂に供える花束の相場は、1束あたりおおよそ3,000円〜5,000円が一般的です。特に一対(二束)でお供えする場合、6,000円〜10,000円程度を目安にする方が多く見られます。
金額に幅があるのは、花の種類やボリューム、地域の慣習などによって異なるためです。予算の決め方が分からない場合は現地のスタッフや花屋さんに相談すると、相場を教えてもらうことができるでしょう。
特に仏教の法事では「慎ましやかであること」が重んじられるため、過度に豪華な花材を避け、白を基調とした落ち着いたデザインが好まれます。法事の場はあくまで供養と静寂の場であることを意識した選び方が求められます。
地域や宗派による差はある?
地域によっては相場に違いが出ることもあります。たとえば都市部では5,000円以上の花束が一般的な一方で、地方では3,000円前後でも十分とされるケースもあります。また、宗派ごとにお供えする花のスタイルや色合いにも微妙な違いが見られます。
浄土真宗では特定の花に制限はありませんが、華美なものは避けるべきとされ、白・黄・紫などの落ち着いた色調が好まれます。一方で日蓮宗では季節の花を中心に比較的自由な組み合わせが許容されている場合もあります。事前に菩提寺や施主に確認しておくと安心です。
本堂用の花束の選び方とマナー

適した花の種類と色合いを選ぶ
本堂に供える花は、「仏花(ぶっか)」としての意味合いもあるため、仏事にふさわしい種類と色合いを選ぶことが大切です。一般的には以下のような花がよく用いられます。
-
菊:仏花の代表。長持ちし、落ち着いた印象を与えます。
-
カーネーション:やさしい印象で幅広い世代に好まれます。
-
ユリ:1本入るだけでもボリュームが出ます。法事に合わせて、開花した状態ものを選ぶとよいでしょう。
-
トルコキキョウ:華やかさを抑えつつ柔らかな印象を与えてくれます。
色合いは、白・紫・淡いピンク・青などが好まれます。ビビッドな赤や黄色、濃いピンクなどは避け、全体的に落ち着いた配色になるよう心がけましょう。
また、香りが強すぎる花(ユリなど)は、会場によっては好まれない場合もあるため、控えめな香りの花を選ぶと安心です。
避けたほうがよい花やスタイル
以下のような花材やスタイルは、法事用の花束としては避けたほうが無難です:
-
バラなどトゲのある花:刺激や攻撃性を連想させるため、仏事には不向きとされています。
-
派手な色やラメ付きの花:法事の厳かな雰囲気に沿わないため
-
ドライフラワー・プリザーブドフラワー:法事の際には生花が基本です。
-
アレンジメントスタイル:置き場所や処理のしやすさを考慮し、花束(束ねた形)のほうが本堂には適しています。※問題ない場合もございます。
仏花としての体裁を意識しながら、過度な装飾や個性的なデザインは控えましょう。上品で控えめな花束が最もふさわしいとされています。
お供え花束を持参するタイミングと渡し方

花束を本堂に供えるタイミングは、読経が始まる前、すなわち法事が始まる少し前が適切です。多くの場合、受付時にスタッフへ預けるか、寺院の指示に従って祭壇や供花台に自分で供える形式となります。
持参の際は、ラッピングは控えめにし、包装紙は外して供えるのが基本です。また、花屋で「法事用に本堂に供える一対の花束で」と伝えると、仏事に適した落ち着いた仕立てで作ってもらえます。迷った場合は、事前に寺院や施主へ相談するのもマナーの一つです。
以上のように、本堂に供える花束には、相場やマナー、地域性など多くの配慮点がありますが、基本は「故人やご先祖への敬意を表すこと」が大切です。控えめながらも心のこもった花をお供えすることで、スムーズに法事に臨むことができるでしょう。