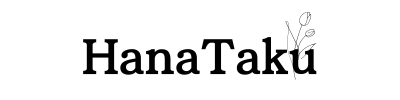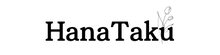敬老の日は「何歳から祝うもの?」
「敬老の日は何歳からお祝いすべきなの?」という疑問を持つ方は多いですが、実は法律や制度上で「何歳から」という明確な決まりは存在しません。国民の祝日としての敬老の日は「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」とされているだけで、具体的な年齢の規定はありません。
つまり、敬老の日をいつから祝うかは、家庭や本人の考え方次第です。
公的には「65歳以上」が高齢者とされる

法的に年齢の決まりはないものの、一般的な目安としては65歳以上が「高齢者」とされることが多いです。
-
WHO(世界保健機関):65歳以上を高齢者と定義
-
日本の老人福祉法:65歳以上を高齢者として各種サービスの対象に設定
このため、公的な基準に合わせて「65歳から敬老の日を意識する」という人も少なくありません。
関連記事:敬老の日に贈りたい花言葉|お祝いの言葉・長寿・健康を願うおすすめの花
60歳の還暦も「敬老の日」のお祝いタイミングに
一方で、日本の伝統的な考え方では60歳(還暦)を人生の大きな節目とみなし、お祝いをする風習があります。
還暦は「生まれた干支に戻る年」であり、古来より「長寿の祝いの始まり」とされてきました。
そのため、60歳を迎えた方を敬老の日で祝うケースも珍しくありません。
【敬老の日】秋のアレンジメント ピンク Sサイズ 3,500円 敬老の日に贈るお手軽サイズの秋色アレンジメント ¥3,850
孫が生まれたら「敬老の日デビュー」という考え方も
最近の傾向として増えているのが、孫ができたタイミングで敬老の日を祝うというケースです。
-
孫が「おじいちゃん・おばあちゃん、ありがとう」と伝える日
-
家族にとって新しい役割を迎える節目
このように、年齢に関係なく「祖父母になった」ことをきっかけにお祝いを始める家庭も多くなっています。
定年退職を機に祝う人も多い
敬老の日は「長年の労をねぎらう」という意味合いも強いため、定年退職のタイミングを機に祝われることもあります。
-
「お疲れさまでした」という労いの気持ち
-
第二の人生のスタートを応援する意味
このように、働き盛りを終えて新しい生活を迎える節目に敬老の日を始めるのも自然です。
70歳・80歳などの長寿祝いに合わせて祝うのもおすすめ

「何歳から」と迷う場合は、長寿のお祝いとあわせて敬老の日を祝うのも良い方法です。
日本には以下のように節目を祝う文化があります。
これらの長寿祝いにあわせて、敬老の日にプレゼントやお花を贈ると、さらに喜ばれるでしょう。
関連記事:敬老の日のお花としてりんどうを贈る理由とその意味|花言葉・選び方・おすすめの贈り方
【敬老の日】秋の花束 ピンク Sサイズ 3,500円 敬老の日に贈る小さめサイズの秋色ピンクの花束 ¥3,850
まとめ|「敬老の日は何歳から?」は家庭次第
結論として、敬老の日に「何歳から」という明確な決まりはないため、家庭や本人の希望に合わせて柔軟にお祝いすれば問題ありません。
一般的な目安をまとめると
-
法律・制度的な目安:65歳以上
-
慣習的な節目:60歳の還暦
-
ライフイベント:孫ができたとき、定年退職のとき
-
長寿祝いにあわせる:70歳・80歳・88歳など
一番大切なのは「ありがとう」「これからも元気でいてほしい」という気持ちを伝えることです。年齢に縛られすぎず、感謝を形にする日として敬老の日を活用してみてください。
【敬老の日】秋のアレンジメント 黄色 Mサイズ 5,000円 敬老の日に贈る定番サイズの秋色アレンジメント ¥5,500